70.三年寝太郎の目覚め
電子書籍を書いています。楠田文人です。
電子書籍はこちら >>
いくら起こしても起きない寝太郎が三年振りに起きた。
「ふぁあ~っ!」
と大きく伸びをして欠伸をすると辺りを見回した。
寝太郎は、ほんの少し寝たつもりだったが、周りは勝手に三年が経っていた。おふくろは三年分歳を取って皺が増えた。歳の離れた妹はきれいな少女になっている。
寝ていた三年間を返して欲しいと思うより、進んだ三年に早く追い付かないと行けないと焦った。
三年間は中途半端な時間だ。十年寝ていたらしっかり時代に取り残されて、追い付くのに苦労するだろう。桃栗三年柿八年。石の上にも三年。微妙な間隔の感覚だ。
とは言え、三年は一年の三倍だ。新橋の飲み屋のボトルは切れちゃっただろうなぁ。駅前商店街の居酒屋で入れた焼酎のボトルはどうだろう。そもそも残ってたっけ?
駅前スーパーのスタンプは溜まるところだった。
「寝太郎さんが起きたって?」
「そうなんです。三年振りに目を覚ましたんですよ!」
「寝太郎さん起きたんだって?」
町では噂が広がった。
寝太郎が天井を眺めているとおふくろが来た。
「高田くんよ」
「高田か。行くよ」
寝太郎は起き上がってガウンを着て居間に行くと高田がいる。
「やっと目が覚めたか? 長かったな、三年だよな?」
「ああ、そうらしい。ついさっき寝たばかりの感じだけど」
「何で三年も寝てたんだろうね?」
「医者でも判らないらしい。単に寝てるだけで他に悪いところはないってさ」
都市伝説は多い。
三年振りに会った高田は少し老けた感じはするものの、寝る前に飲んだ時とほとんど変わらない。様子がちょっと違って見えるだけで、それ以外は前と同じだ。
「高田は少し痩せたのか?」
「五キロくらい痩せた」
こう言うところに三年経ったことが現れる。
「寝太郎が寝たきりになる前に飲んだじゃん。その時のこと覚えてる?」
「覚えてる。駅前の焼き鳥屋」
「あん時、駅前で待ち合わせてる時に、一緒に宝くじ買ったじゃん。俺は全く覚えてなかったんだけど」
「うん」
「百円のくじを、連番とバラを千円ずつ出して二十枚買って、十枚ずつ分けた」
なんとなく思い出した。
「忘れてて、昨日当選番号を確認したら、俺の分の連番の一つ前のが当たってたんだ。あん時の宝くじどうした?」
高田の持ち分の一つ前と言うと、連番の一桁が五のくじか。
「どこに入れたかな? 着てたスーツのポケットか、バッグか。当たってた?」
「一千万円」
がちゃん!
茶碗を落とす音がした。慌てたおふくろが部屋の障子を開けた。
「一千万! あんたどこに仕舞ったの?」
お茶を持って来たところ廊下で聞いたらしい。
「早く探しなさいよ」
おふくろの方が慌ててる。
「判った」
寝太郎は思い腰を上げて部屋に戻った。

「知らなかった。宝くじの当選金引き換えは一年以内なんだってさ」
「俺も買ったことをすっかり忘れててさ、それに、お前が寝た切りで起きないって状態になっただろ。すっかり頭から抜けてた」
高田も忘れてたらしい。目覚めて余裕の出てきた寝太郎は言った。
「一千万分の夢を三年間見てたことになるかな」
「そんないい夢を見たのか?」
「それは言えない。ふわぁあ~」
寝太郎はにやっと笑った。
69.アーティチョークを探した
電子書籍を書いています、楠田文人です。
電子書籍はこちら >>
高校の時、友人が伊丹十三に ハマってまして、追っかけじゃなくて「女たちよ」と言うエッセイのファンで、「おもしろいから読んでみな」と貸されました。確かにおもしろい。○○の話とか、△△の話とか、□□の話とか(※ネタバレになるので書けません)、今読むと高校生向きの本ではなかったと思う。
伊丹十三の「女たちよ」はこちら >>
エッセイで色々な話が登場します。食べる話に登場する「アーティチョーク」がおいしそうで食べてみたかった。
当時、レストランで初めて「カニクリームコロッケ」「ライスグラタン」とかを食べた時は、その味に驚いた記憶があります。ハンバーガー、フライドポテト、フライドチキンも次第に日常的な食べ物になりましたけど、初めて食べるとそれまでの食生活では出会わない味なので結構びっくりする。
「アーティチョーク」は大きな松ぼっくりみたいな形をしていて、隙間に入ってる実だか種だかを食べるらしい(今となっては記憶が定かではない)。どう考えても八百屋で売ってる気がしない。友人は近所の八百屋に行ったけど見付からなかったようです。
「済みません」
「あいよ! 何を差し上げましょう」
「アーティチョーク、ってありますか?」
「あーてぃ!? 何だいそりゃ?」
「アーティチョークって言うらしいんだけど」
「チョークって、白墨を食べるのかい?」
※ 黒板に板書するチョークは白墨とも言いましたよね
「アーティチョーク」は「西洋アザミ」と言うそうな。これまた植物の知識がないので見当も付きませんが見付からないので諦めて以来、未だに食べていない。
伊丹十三は、ブラザース・フォアのベストアルバムの中に収められていた「北京の 55 日」と言う曲のライナー・ノーツで知っていました。同じ題名の映画の主題歌で、映画に伊丹十三が出演していたらしい。見てないけど。
「北京の 55 日」はこちら >>
昔の洋食で思い出すのは、スパゲティはナポリタンが普通で、って言うかそれしかない時に初めて食べたミートソースです。今は無き渋谷駅玉電ホームにあったコーヒースタンドのミートソースはソーセージが入ってた。こちらも驚きの味でした。
それから、田園調布と自由が丘の中間あたり、環八から少し入ったところにあったドライブイン「ヴァンファン」のドライカレーは、カレーピラフではなくてご飯の上にキーマカレーを乗せて、その上にポーチドエッグを乗せたものでした。懐かしい。
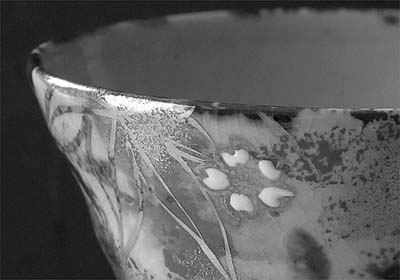
「ただいま」
「お帰り」
「おう、花子」
「何だい、父ちゃん?」
「今日、学生さんが白墨買いに来たけどよ」
「白墨!?」
「そうだよ」
「八百屋で売ってる訳ないじゃん!」
「俺もそう言ったんだけどよ」
「売り始めたのかなぁ」
花子の言葉に『白墨、売り切れました』の札を下げることにした。話は後で考えりゃいい。
翌日のことだ。
「いらっしゃい!」
作業着を着た老人が札を見詰めている。主人は老人に声を掛けた。
「白墨ですか?」
「ええ。売り切れって、いつ入って来るんですか?」
注文だ!
「お取り寄せになります」
「それじゃ、白を 1 カン頼む」
そう言うと老人は行ってしまった。翌日から主人は白墨問屋探しが始まったのである。
68.何となく前回の続き
電子書籍を書いています。楠田文人です。
電子書籍はこちらへ >>
ドアが開いた続きを考えました。
白いペンキの剥げかかったドアが開いて、暖かそうな茶色のコートを着た男が入って来た。靴が雪を踏む音を立てた。ささくれたドアに雪が溜まって行く。肩に付いていた粉雪が、室内の暖かさに消えた。
「いらっしゃいませ。雪が降って来ましたね?」
カウンターに立っていた髭のマスターが声を掛ける。
「まだぱらぱらですよ」
男は答え、奥に座る女性の席に行った。店に他の客はいない。
「頼んだの?」
男はコートを脱いで、向かいの席に座った。
「来てからにしようと思って」
「頼んでないの?」
「ええ」
マスターが水とお絞りをテーブルに置いた。
「何になさいます?」
「生ビール。中ジョッキふたつ」
男はメニューも見ずに言う。店に慣れている感じだ。
「毎度ありがとうございます」
マスターはカウンターの中に戻って棚からジョッキを出した。
男が席に着くと女性は紙挟みを取り出して書類を広げた。
「まだこれだけか?」
二枚目、三枚目と書類を見た男が言う。
「返事が遅いのは年末に近いからだと思うわ」
「まあ、仕方ないか」
ジュワッ、ジュワッ!
マスターがジョッキをカウンターに置き、エプロンを脱いでいる。
「済みませんね。樽が終わっちゃったんで、新しいのを取って来ます」
そう言ってカウンターを出てドアを半分開けた。
「うっ、寒い!」
雪の降り方が強くなったらしい。この時期なのに、半袖ポロシャツとベストと薄着のマスターはビニール傘を差して表に出て行った。
「新しい樽を取りに行ったの?」
「そうだろう。あの格好だから近くの倉庫に置いてあるんだろう」
二人は窓の外を見た。粉雪だったのが本降りになって来た。
「綿貫さんは飯塚さんから連絡してくれるって。こっちの法学部の人は村元くんに頼んだ」
「この分は経済の連中に頼めばいいか」
二人はリストを見ながらテキパキ作業を進める。女性がコップの水を飲んだ。
「ビール頼んだんだよ」
男が咎めるように言い、女性は慌てて止めてコップを置く。
「いっけない! マスターはまだ? あっ!」
いつの間にか窓の外に広がる雪景色。レンガ塀の上に積もる雪。止めてあった車に雪が積もり始めている。静けさの中にチェーンを撒いたタイヤの音が急に大きく聞こえて来た。
「ありゃぁ! こんなに降ってたんだ」
男も手を止めて外を見た。
「マスター、雪で戻れなくなったのかしら…」
「そう言や遅いね」
「大丈夫かしら」
--- マスターはどうしたんだろう。ここで事件が起きるか、状況が変わらないとお話が展開しませんね。例えば、
ガチャ。
溜まった雪を押し分けて男が入ってきた。
ドッ、ドッ、ドッ。
男は頭や肩に積もった雪を振りはらい、窓際の客に聞く。
「マスターは?」
「ビールの樽を取りに出て行きましたよ」
「そうですか」
男はカウンターの席に座り、重ねられた灰皿の山から一つ取った。
--- こんな感じ。常連らしき人が入って来ました。もっと客を増やそう。
ガチャ。
「寒~い」
ザッ、ザッ。
また客が入って来た。今度はカップルだ。ヒマラヤにでも登るのかと言うほどの厚着をしている。
「マスター、いないわね?」
「どうも」
「あ、どうも。マスター、外に行ったのかな?」
男はカウンターを見た。カウンターの男が会釈して、入ってきた二人はカウンターの隣の席に着く。
ガチャ。
また客だ。今度は寒そうなスーツ姿の男だ。書類入れを持った手が震えている。先に入ってきた客に挨拶してるのか、寒くて頭を震わせているのか区別が付かない。
その後も客は続き、マスターがいないのに、店はあっという間に満席になって仕舞った。店内は賑やかで飲んでもいないのに会話が飛び交う。
ヒマラヤの男が立ち上がった。
「済みません、済みません。ちょっと話を聞いてください!」
客は何事かと静まり返った。
「今日はマスターの誕生日なんです」
「おおー!」
店内は拍手で盛り上がる。
「そこで、うちのかみさんと考えました」
ヒマラヤの男は、真っ赤なリボンが結ばれた青いプレゼントの袋を掲げた。
「一度、マスターに何が好きか聞いたことがありまして」
客達の期待は高まっている。
「こうなるとは思わなかったね?」
窓際の席に座った男が小さな声で女に言う。女は激しく頷いている。
ガチャ。ドアが開いた。
「あっ!」
「どうした!?」

--- ドアが開いた後、全く違うパターンだとどうなるか。
ガチャ。ツッ、ツッ、ツッ。ブルブルッ。
溜まった雪を押し分けてキツネが入って来た。キツネは頭や肩に積もった雪を振りはらい、こちらをチラっとみてカウンターの席に座った。驚いた女は目を丸く見開いて言葉をなくした。
キツネはとても行儀がよく、背筋がまっすぐに伸び、顔は正面を向いてじっと座ってマスターが戻るのを待っているように見える。
それを見た男と女も、なんとなく背中を伸ばして座りなおした。マスターが飼ってるキツネなのか、それともお客のキツネなのか、マスターが戻らないと判らない。
ガチャ。ドアが開いた。
「あっ」
女の驚いた声を聞いて男がドアを振り返る。
「あっ」
キツネの登場するお話を書いています。
金色のキツネが登場する「東多魔川鉄道物語」はこちら >>
さあてどうしよう。